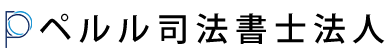公正証書遺言
遺言は、法律に定められた方式に従って作成されなければ無効になってしまいます。
遺言の方式には「普通方式」と「特別方式」の2種類があり、それぞれ書き方や必要な手続きが違います。
遺言を誰のために作成しておくのかということを考えると、不備があれば無効になる可能性の高い自筆証書遺言や、内容が不明確になりがちな秘密証書遺言よりも、法律的に確実な書類であり、相続開始後検認手続きをすることなく遺言の執行が可能な、公正証書遺言が最も安全であり、確実であると言えます。
当事務所ではこれをふまえて、公正証書遺言で作成することをおすすめしております。
- 相続時の手続きがスムーズに 遺言書があれば、その内容に沿って手続きするだけです。遺産分割協議をする必要もないので手続はスムーズになります。また、『遺言執行者』と言う事務管理者を指定することで、手続をすべて任せることもできます。
- 公正証書遺言では検認手続が不要 自筆証書遺言、秘密証書遺言は被相続人の死亡後、家庭裁判所において検認の手続が必要になりますが、公正証書遺言では検認手続が不要です。当司法書士事務所では、この点からも公正証書遺言をみなさまにおすすめしております。
- この先何か起きても意思を尊重 この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、遺言を作成しておけば、何が起きても、ご自身の意思を反映することができます。
遺言の書き方
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が定められています。
これを要式行為といいますが、遺言者の最終意思を明確にして、争いを防ぐために厳格な方法を定めています。ここでは、一例を説明させていただきます。
さらに詳しくお聞きになりたい場合などのは、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
- 遺言の取り消しの方法 遺言者が遺言書を作成後、時が経つのや心境の変化などにより、遺言の取り消しをしたいと思った場合は「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部又は一部を取消すことができる」と民法で定めています。よって、遺言者は誰の同意もなく、いつでも自由に遺言書の内容を変更したり取り消したりすることができます。
- 以前作成した遺言書を取り消す旨の記載をした遺言書の作成 「平成○年×月△日作成の遺言は全部取消す」というような、以前に作成した遺言書を取り消す旨を記載した新しい遺言書を作成します。
遺言に関するよくある質問
- 自筆証書遺言とは、どんなものですか?
- 自筆証書遺言は、遺言書が自分1人で作成することができます。
本人が全文、日付、及び氏名を自筆で書き、捺印することで成立します。
あくまで自筆ですので、字が書けなければこの方式によることはできません。
その場合は公正証書遺言によることになります。 - 以前、遺言書を作成したのですが、その後考えが変わりました。書き直すことはできますか?
- はい、できます。民法1022条で、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる」と規定されています。
- 遺言は何歳から認められますか?
- 15歳に達せれば、親の同意がなくても遺言することができます(民961条)。14歳以下の者は親の同意があっても遺言することはできません。
- 父が亡くなり、遺言書がありません。どのような手続が必要ですか?
- 遺産を法律で定められた割合(法定相続分)で分配して相続することもできますが、法定相続分とは違う割合で相続をしたい場合は、遺産分割協議書の作成が必要になります。